40代半ば頃だったと思う。世の中では断捨離が流行り、自分もいろいろと整理をしていた。すると中学校時代の国語副読本がでてきた。ぺらぺらとページをめくる。懐かしさが蘇った。本当に勉強しなかったな-。本の中に小説「高瀬舟」(森鴎外)があり、時間もあって読むことにした。
驚き
喜助は弟殺しの罪で、遠島送りになる。同心羽田庄兵衛は護送役として船に乗り込む。一般に罪人は悲しみにくれるのに、苦にする態度が見えない喜助に、庄兵衛はその理由を問う。するとこれまでは仕事を見つけては身を粉にして働き、もらった銭で借金を返し、返してはまた新たに借金をしてという貧しい生活。それが牢に入ると食事を与えられ、遠島で少しばかりのお金も渡され、はじめて自分の貯蓄を持った喜びを喜助は語る。それを聞き、庄兵衛はわが身を振り返る。女房に4人の子供。倹約をしていて、衣類も最小限。喜助とはけたが違う扶持米をもらっても、それを左から右へと人手に渡して暮らしているにすぎない。そんな話を読み、住宅ローンを抱え必死に働くわが身が庄兵衛に重なった。舞台は江戸時代、鴎外が書いたのは明治、平成に生きる自分。時代は変わっても、似たような生き方をしていることが驚きだった。
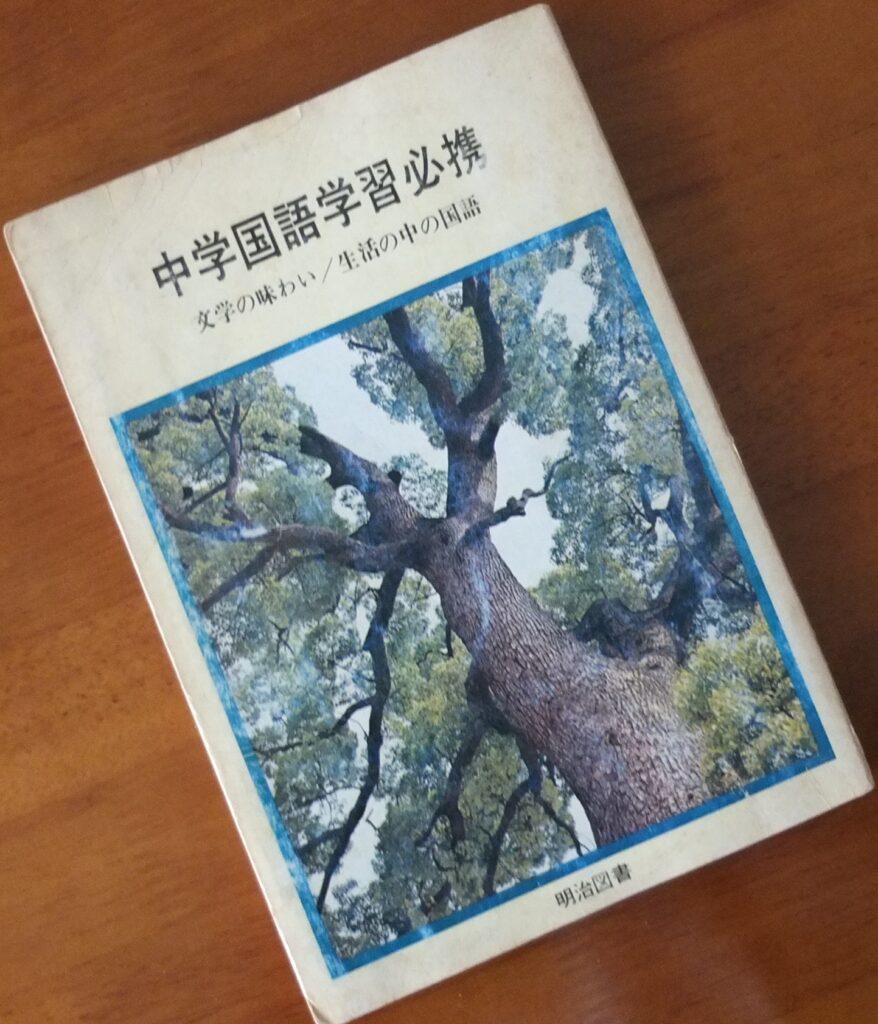
飲み会で
この気持ちを飲み会の席で話をしていると、ある先輩が、それはちょっと論点が違うのではないかな-。高瀬舟は、貧しい中必死に働く兄に、迷惑をかけたくない病気の弟が自害をはかる。死にきれず苦しんでいるところを、兄が助けようとした。しかし、うまく助けられず結果として弟は死亡する。その兄を人殺しとして罪を問えるのか、というのが論点ではと言った。
授業を思い出す
そういわれ、中学時代の授業を思い出した。グループをつくり確かにそのテーマで議論をしたことを。そしてもう一つ思い出したのは、当時先生が、君たちにはわからないだろうなと少し笑いながら話をしたこと。収入を得ては、それが出て行ってしまうこと。厳しさと言ったか、やりきれなさと言ったか。先生が授業で話せば、理解しなさい、覚えなさいとうのが普通あったが、わからなくて良い、大人になればわかると言って話すのは、何か新鮮な感じがした。そんなことを飲み会の先輩の一言で思い出した。
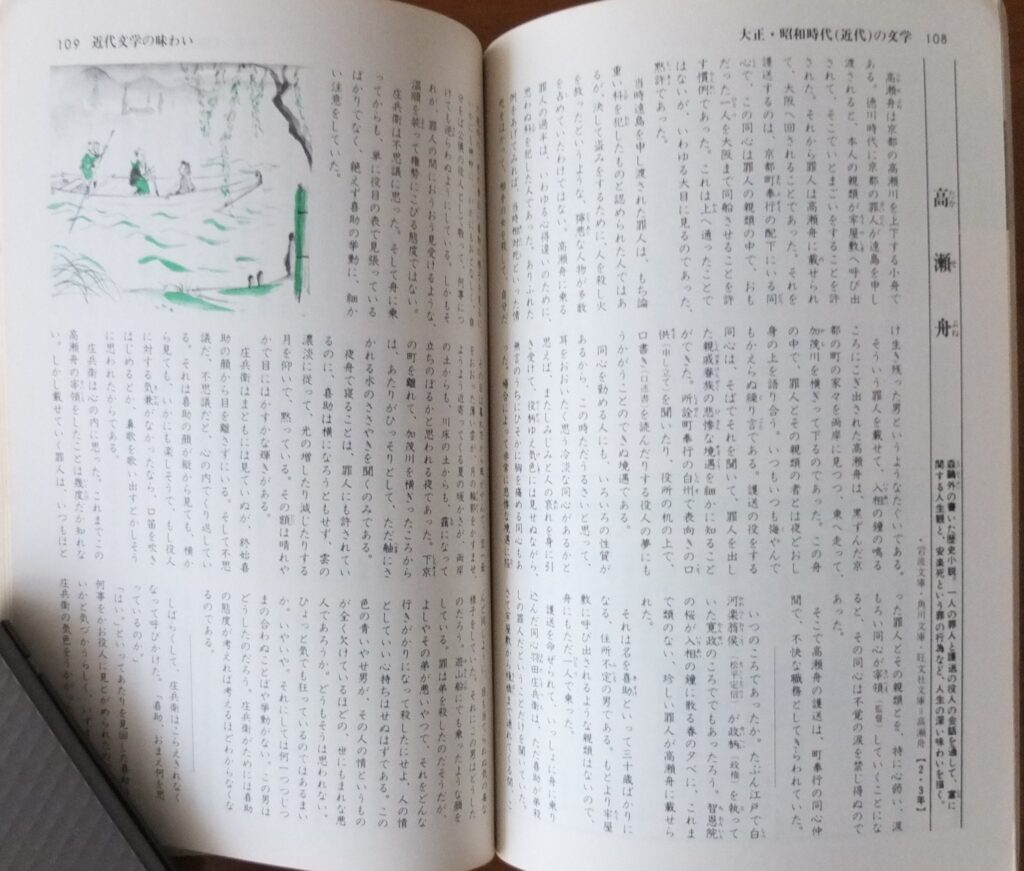
永遠のテーマ
高瀬舟を要約、解説するのは、私には力不足だ。万一読んでいない方は読んでみてください。さまざまな読み方ができるのだろうけど、「吾足るを知る」は、重要なテーマの一つだろう。その境地にいけるのだろうか。



コメント